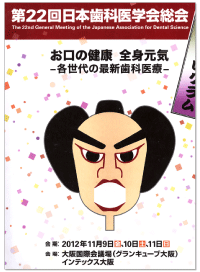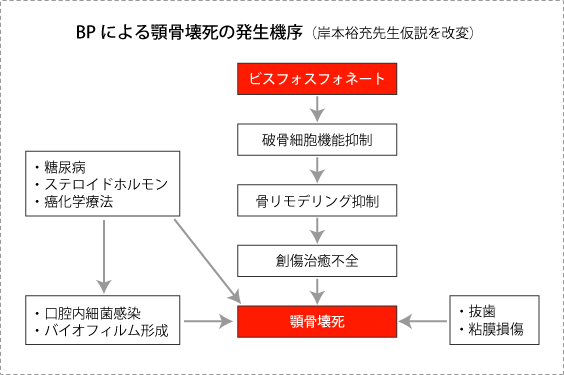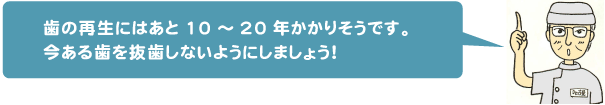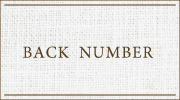さいたま市浦和区の歯科医院 歯周病予防 虫歯予防 矯正 歯の定期検診
生涯ご自分の歯で過ごせる喜びを

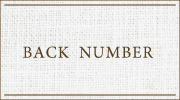
Home >> ハ・は・歯のニュース12年12月号

口腔ケア(怠ると全身に影響)
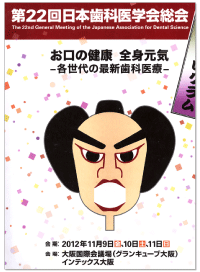
- 山中伸弥先生、高橋和利先生の「iPS細胞研究の進展」から
- 山中、高橋先生の講演から。2006年にマウスの皮膚の細胞からES細胞様の細胞を作り出し、この細胞を人工多能性幹細胞(iPS細胞)と命名した。
翌年にヒトiPS細胞を樹立することに成功。これにより皮膚の細胞など分化した体の細胞から作ることができるため、自家移植ができ、拒絶反応のリスクを減らすことができた。再生医療への道が開けた。しかし、再生医療への応用にはいくつかの課題がある。癌化しないi
PS細胞の樹立、拒絶反応の少ない細胞のストック方法などである。2020年までにiPS細胞のストックを構築、臨床試験の開始、患者由来のiPS細胞による治療薬の開発に貢献する。
- 歯科における再生医療
- 歯科における再生医療はマウスを使い抜歯した個所に歯を再生する研究が行われている。
再生歯胚を移植する方法と既に完成している再生歯を移植する方法がある。東京理科大学研究機構 辻孝教授たちは歯と周囲の歯根膜、歯槽骨を含めた「再生歯ユニット」をつく出すことに成功した。この再生歯ユニットを移植することにより早期に再生歯を機能化させることができるようになった。ヒトの歯の再生にはヒトでの最適化、臨床試験、安全性の評価を含めると20年近い期間が必要であろうと辻教授は述べている。
- 「最新!ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の臨床」から
- 岸本裕充先生の講演(兵庫医科大学 准教授)より
- 顎骨壊死はビスホスホネートにより骨代謝が異常をきたした時に、口腔内で感染すると発症につながるということが分かってきた。そのため、抜歯などしてなくてもBP製剤を投与している患者さんに、顎骨壊死(BRONJ)が自然発症している例が見られたという。
1570症例の調査で、 67%が抜歯、26%が自然発症、その他7%という結果がある。 他の4129例の調査では経口薬での顎骨壊死は約1%だった。骨粗鬆症の薬と顎骨壊死との関係は,いまだに結論がで出ていない。そのため、予防としては、口腔清掃を徹底することが一番重要である。
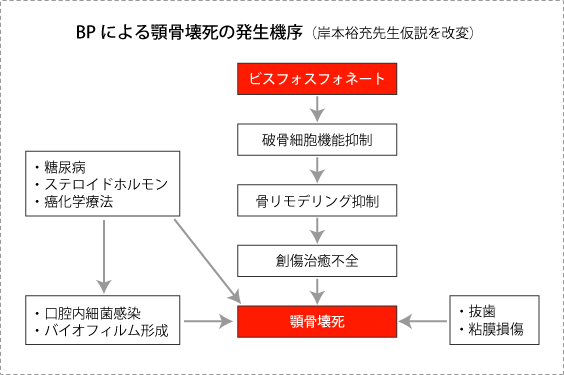
- 日本歯科骨粗鬆症研では
- 日本歯科骨粗鬆症研/学術大会(2012.3)で、慶応義塾大学スポーツ医学センター岩本潤先生は「BPは脊椎・大腿骨骨折に予防効果があり、第一選択薬となるが、
顎骨壊死のリスクを抑えるため、うがい・歯磨き・手洗いの励行を指導している。」と述べています。
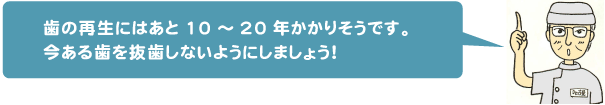
ページトップ
HOMEに戻る