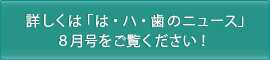Home >>
愛歯会だより

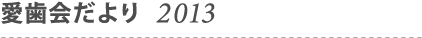
- 愛歯会は、古屋医院が主宰する、歯の健康を考え実行する人たちの集まりです。どなたでもご参加いただけます。1993年以来、年に1〜2回、愛歯会の集いを行っています。集いには歯科以外の各科の現役医師の方々を講師としてお招きし、健康に関する役に立つ講演をお願いしています。
- 愛歯会 会長:上岡 悦子 古屋歯科医院 院長:古屋 紀一
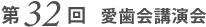 (H25.7.20.)
(H25.7.20.)- 上岡愛歯会会長のご挨拶
- メンテナンス優秀者表彰
- 古屋歯科医院院長 古屋紀一による歯のミニ講演 「よく噛んで健康を!」
- 東京医科歯科大学 教授 泰羅雅登先生による講演 「脳を健やかに」

講演:泰羅雅登先生
(東京医科歯科大学 教授)
- 脳は「使うことにより変化する」
- 私たち脳は意外といい加減です。私たちの眼はしっかり見えているのは注視している部分だけで、周辺はぼやけてしか見えていない。この像を補うのは脳である。しかし、脳は都合よく解釈をしたり、顔は必ず出っぱっているなど思い込みをもって解釈し、コンピュータのように精密な分析はおこなっていない。この脳は10歳ころまでに大人と同じように育ち、そのあとは体が老化するのと同じように老化する。しかし、このような形の変化以外に脳には「使うことによる変化」という素晴らしい能力を持っている。
- 脳を健やかに保つコツ
- 脳を健やかに保つコツは「使うことによる変化」を絶えず起こさせることである。特に、他の人とコミュニケーションを取りながら、やった、できたという達成感を感じることが重要である。人は学びの動物であり、何歳になっても学ぶ好奇心を持ち続けている。口を動かすことも脳に刺激を与える。おいしいを感じるためには健やかな脳がなければならない。逆においしいと感じることは生活に張りを与えてくれ、脳を健やかに保つことにもつながる。そのためには入り口である口のメンテナスが重要なのである。

講演:古屋紀一先生
(古屋歯科医院 院長)
最近では何を食べるかに、異常に関心を持つ人が多くなっています。テレビや新聞などで、この食べ物が体に良いと報道されると、その日のうちに、品切れになります。しかし、食べ物を体内にどのように取り込むかには、あまり関心がないように見えます。 噛むことがどんなに重要なのか、知らないし、関心がない方が多いようです。 今回の愛歯会ミニ講演では、よく噛むことがどのように体の健康に結びついているかについて、お話しいたします。
- よく噛むと → 唾液が出る →唾液が出ると唾液のいろいろな物質が体の健康をサポートします。
-
- 消化酵素(アミラーゼなど)が多くなる
- 歯の汚れの除去(自浄作用)が期待できる
- 粘膜(口腔、食道)の傷が修復されやすい
- 歯のエナメル質を保護し、再石灰化を促進する
- 抗菌作用や免疫作用を強化する
- 食物に入っている発がん性を減弱する
- 活性酵素の働きを弱める
- よく噛むと → 食欲中枢を刺激し食べ過ぎない
- 群馬大学医学部、内科の清水弘行先生によるとゆっくりよく噛むと、咬筋からの刺激が脳へつたわり、脳内のヒスタミン神経系を活性化し、食欲を低下させるようです。また、 時間をかけて噛むことにより、食べ物がゆっくりと胃にはいるので、血糖値の上昇や,血中の食欲ホルモンの分泌が抑制され、脳が満腹と感じて食欲を抑えるので、食べ過ぎないことになります。
- よく噛むと → 脳を活性化する
- 噛むことにより、大脳を刺激し、学習能力や記憶能力を高めるという報告もあります。 本日は脳科学者の泰羅先生の講演にこれはお任せしたいと思います。
- よく噛むと → 筋肉鍛えて、老顔貌予防する
- よく噛むと、特に口の周りの「口輪筋」が動きます。口輪筋は顔のいろいろな表情筋ともつながっていて、口輪筋を動かすと顔や首の筋肉も活性化されて、唇の形、口元、頬など顔全体だけでなく、首引き締め効果もあるそうです。口輪筋をトレーニングする装置、「とじろうくん」も売り出されています。
愛歯会講演履歴
- 日時
- 演題・講演者(敬称略)
- ミニ講演(古屋院長)
- 1
- 1993.09
- <成人病が心配ですか?>
埼玉社会保険病院 院長 : 鈴木裕也 - <愛歯会の意味>
歯の健康を守るために
- 2
- 1994.02
- <コミュニケーションとれてますか?>
現代コミュニケーション 所長 : 坂川 山輝夫 - <8020運動とメンテナンス>
- 3
- 1994.09
- <もっともっと健康になるために>
救急救命東京研修所 教授 : 本松 茂 - <メンテナンスにおける
フッ素塗布の意義>
- 4
- 1995.03
- <後藤九五さん(患者さん)治療について>
杏林大学 耳鼻咽喉科 教授 : 長谷川 誠 - <私の歯科治療体験>
- 5
- 1995.09
- <砂漠の文化ーイランの風土、生活、宗教>
大東文化大学国際関係学部 教授 : 原 隆一 - <自分で治せるムシ歯>
- 6
- 1996.02
- <楽しく更年期を過ごそう>
埼玉社会保険病院 産婦人科部長 : 北井啓勝 - <唾液とムシ歯の関係>
- 7
- 1996.09
- <ウォーキングは健康への第一歩>
埼玉県立衛生短期大学 教授 : 佐久間 淳 - <皆さんの安全を守るために>
感染防止対策
- 8
- 1997.03
- <消化器系癌の早期発見法と低侵襲手術法>
埼玉社会保険病院 外科手術部長 : 橋本光正 - <噛むことが脳を活性化する>
- 9
- 1997.09
- <乳癌の早期発見法と最新外科療法について>
埼玉社会保険病院 外科部長 : 洪 淳一 - <ムシ歯と甘味料>
- 10
- 1998.02
- <若返りの秘訣は脳神経細胞の活性化から>
小野耳鼻咽喉科医院 副院長 : 小野昌子 - <愛歯会の意義>
メンテナンスの重要性
- 11
- 1998.09
- <病気と食事>
埼玉社会保険病院 内科部長 : 丸山太郎 - <全身の健康は歯の健康から>
- 12
- 1999.02
- <アレルギー病はなぜ増えたのか?>
東京医科歯科大学医学部 教授 : 藤田紘一郎 - <子供の歯をムシ歯から守ろう>
- 13
- 1999.09
- <痛みと鎮痛ターミナルケアは快適に>
日本医科大学 教授 : 宮田雄平 - <口臭とその対策最新情報>
- 14
- 2000.02
- <ダイエットはこう考えましょう>
埼玉社会保険病院 教授 : 鈴木裕也 - <根管治療はここまで進んだ!!>
- 15
- 2000.09
- <中高年の腰痛について>
埼玉社会保険病院 整形外科部長 : 泉田良一 - <歯周病菌、ムシ歯菌が
引き起こす病気>
- 16
- 12001.03
- <きちんと治そう皮膚病>
久保皮膚科医院 院長 : 久保和夫 - <金属入れ歯による
アレルギーの予防対策>
- 17
- 2001.09
- <病気の予兆とその対策>
山崎外科医院 院長 : 山崎淳之祐 - <ムシ歯や歯周病菌を減らす
最新予防法>
- 18
- 2002.03
- <気になる「排尿の話」>
埼玉社会保険病院 泌尿器科部長 : 石井泰憲 - <寝たきり人の口腔ケアー>
- 19
- 1993.09
- <ワインの正しい知識と飲み方>
シュバリエ : 辻 綾子 - <歯周病に気をつけましょう>
- 20
- 2003.04
- 21
- 2003.10
- <デジタル時代に生き抜く>
話は通じないマナー低下常識は変る
現代コミュニケーション 所長 : 坂川 山輝夫 - <徹底した治療と
定期検診の重要性>
- 22
- 2004.04
- <痴呆を正しく理解しよう>
21世紀はこころの時代
野村クリニック 院長 : 野村和広 - <歯周病予防>
- 23
- 2004.10
- <眼の病気と治療>
埼玉社会保険病院 眼科部長 : 川島晋一 - <歯の破折と防止>
- 24
- 2005.03
- <花粉症の治療について>
おく耳鼻科クリニック 院長 : 奥 常幸 - <介護に必要な口のケアー用品>
- 25
- 2005.11
- <大腸癌について>検査と治療方法
埼玉社会保険病院 : 久 晃生 先生 - <愛歯会の意味>
- 26
- 2006.06
- <脳卒中は予防できる>
メタボリックシンドローム
新都心たざわクリニック 院長 : 田澤俊明 - <歯周病菌が全身を狙っている>
- 27
- 2007.06
- <肩こり・腰痛・手足のしびれ>
自分で対処できる体の痛み
まさ整形外科クリニック 院長 : 佐藤雅史 - <むし歯の予防と食生活>
- 28
- 2008.06
- <日本人乳がんの動向とその治療>
こう外科クリニック 院長 : 洪 淳一 - <怖い!歯のひび割れと破折>
- 29
- 2009.06
- <始まった裁判員制度について>
前検事総長 弁護士 : 但木敬一 - <抜かずにすんだ歯の症例>
- 30
- 2010.06
- <命、その謎と不思議>
埼玉社会保険病院 名誉院長 : 鈴木裕也 - <骨粗鬆症の薬と顎骨壊死との
危険な関係>
- 31
- 2012.09
- <小児外科って、なに?>
埼玉県立小児医療センター 医学博士 : 古屋武史 - <いま歯科に起きている危険なこと>
- 32
- 2013.07
- <脳を健やかに>
東京医科歯科大学 教授 : 泰羅雅登 - <よく噛んで健康を!>